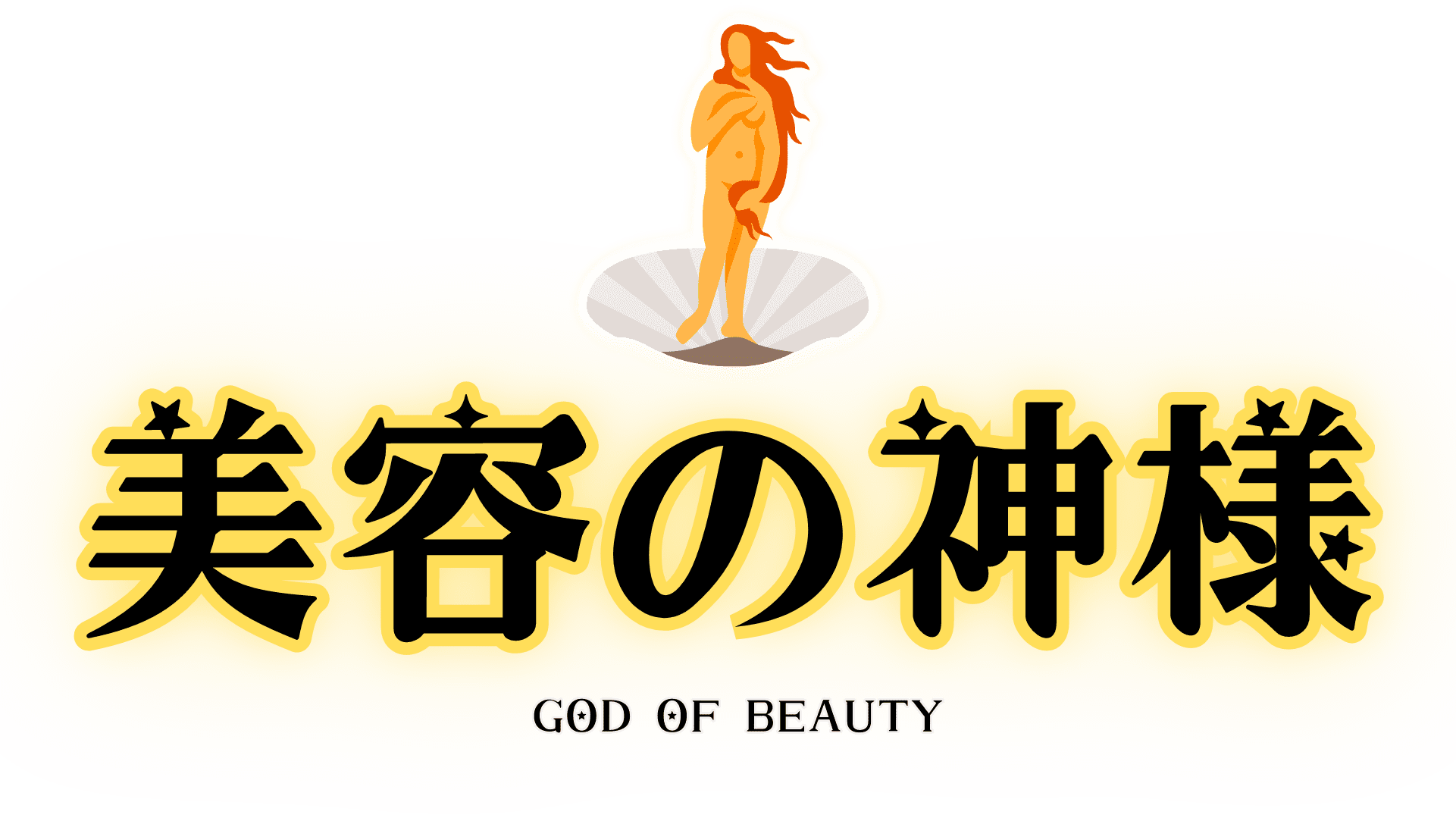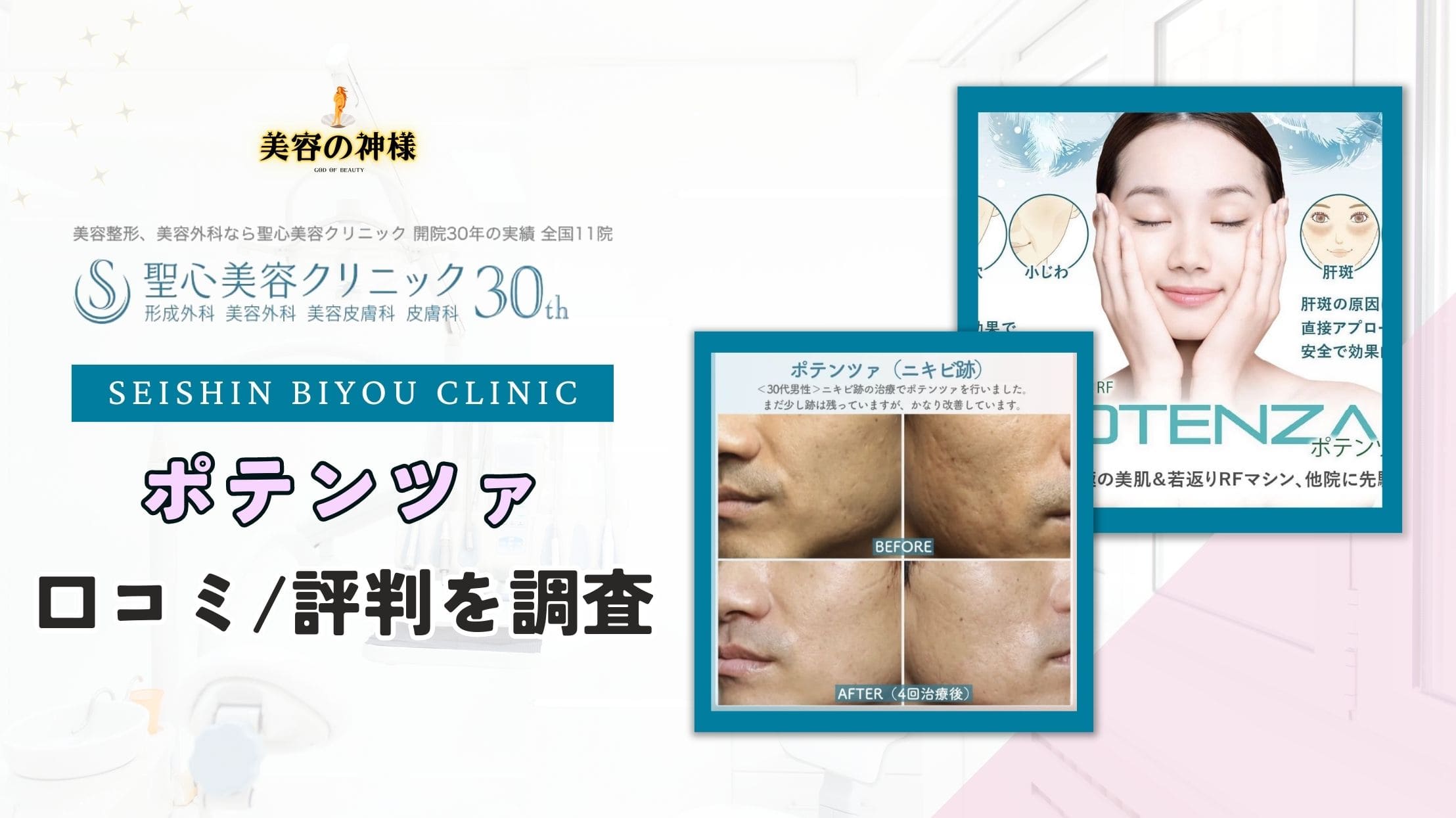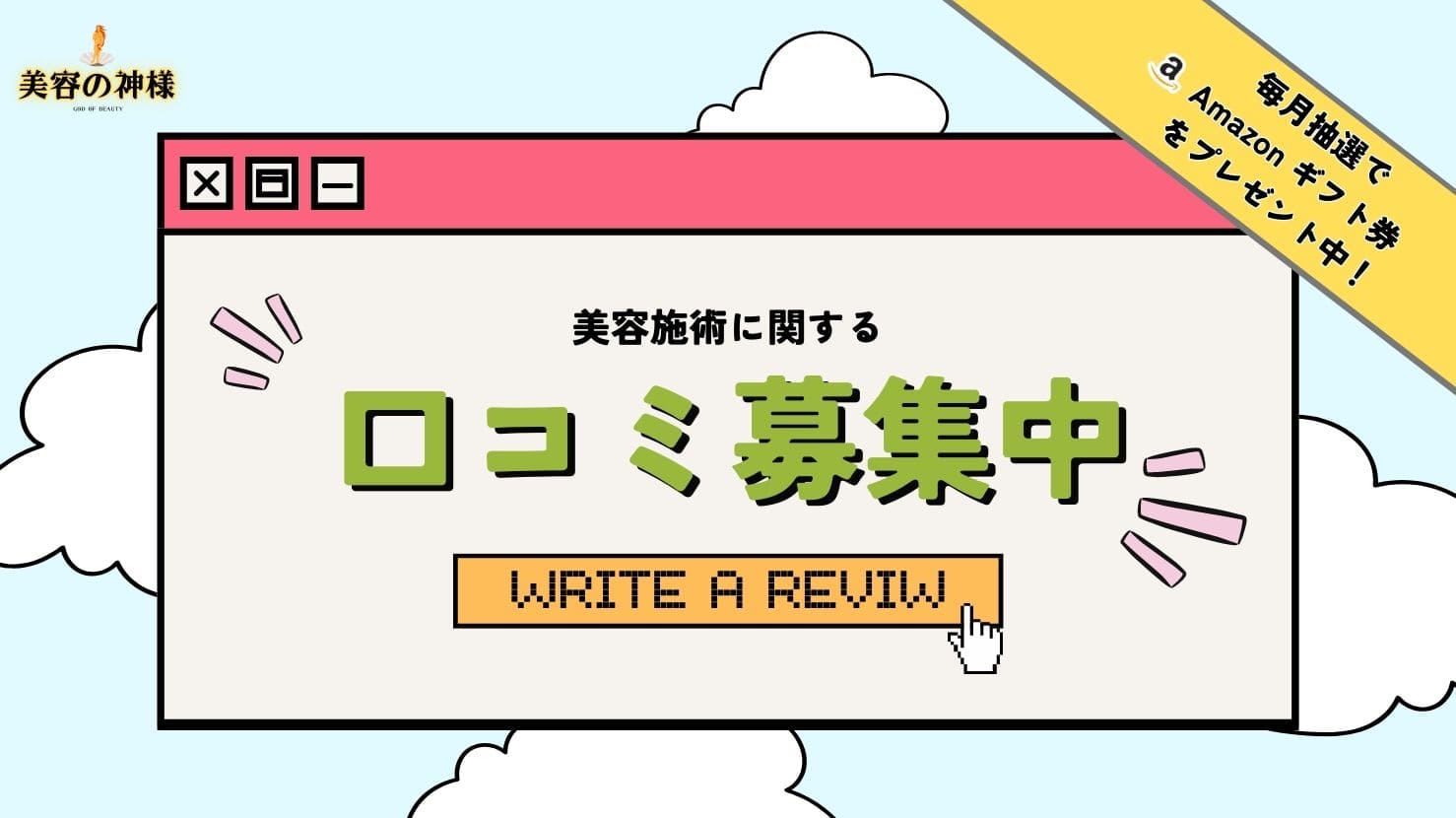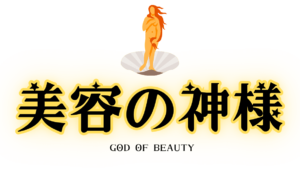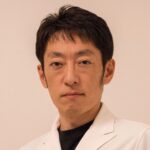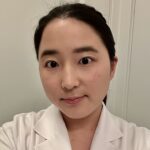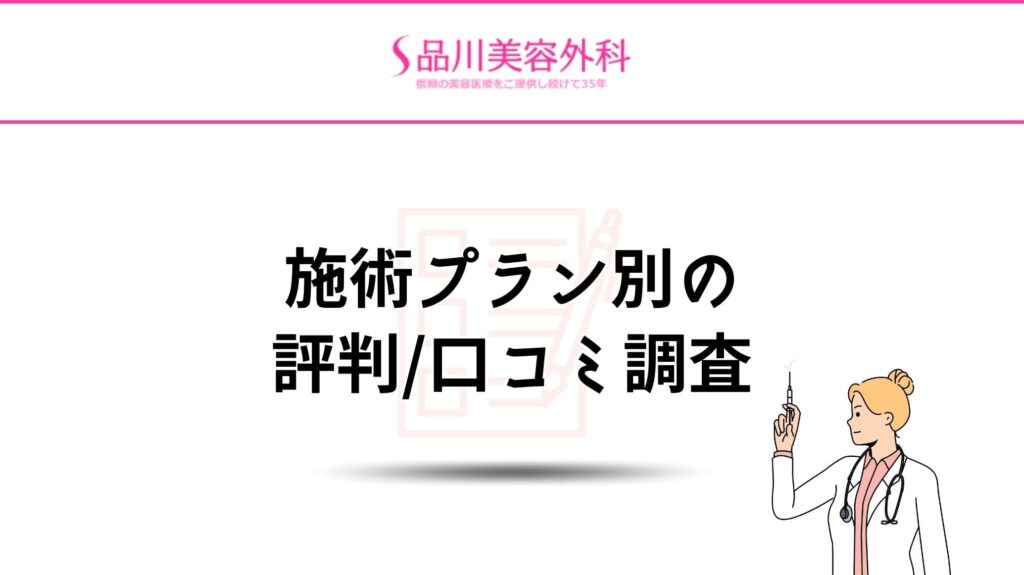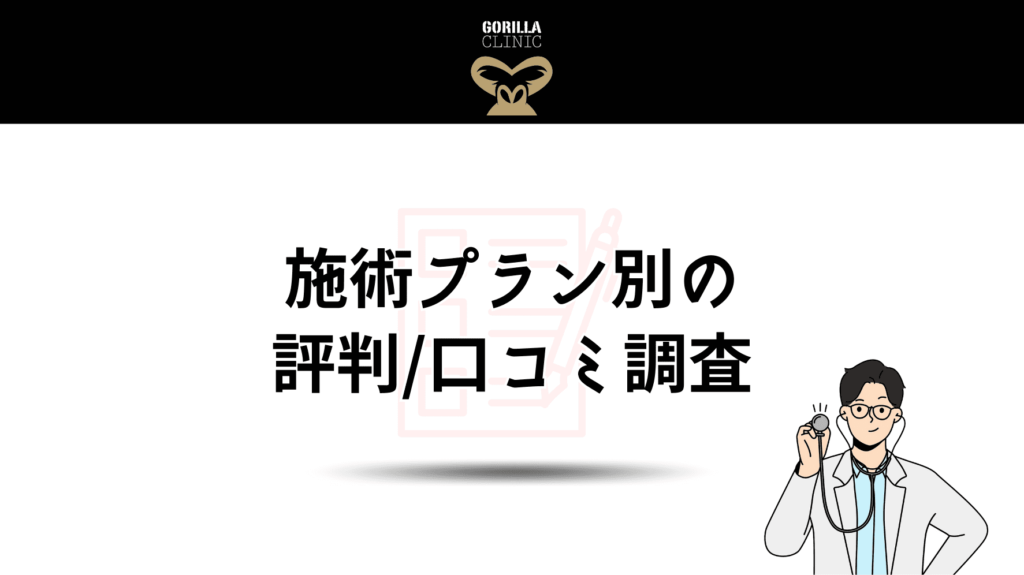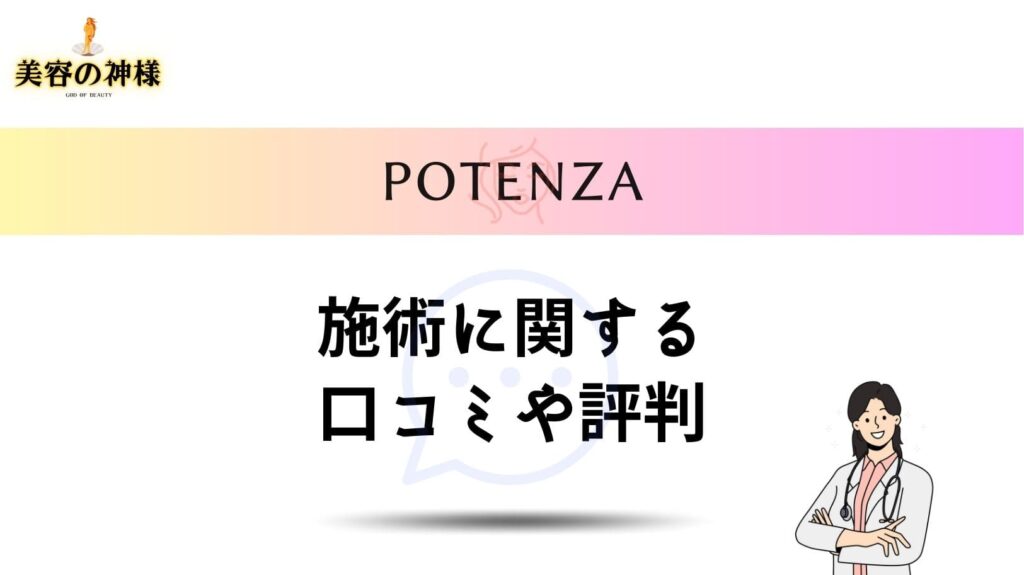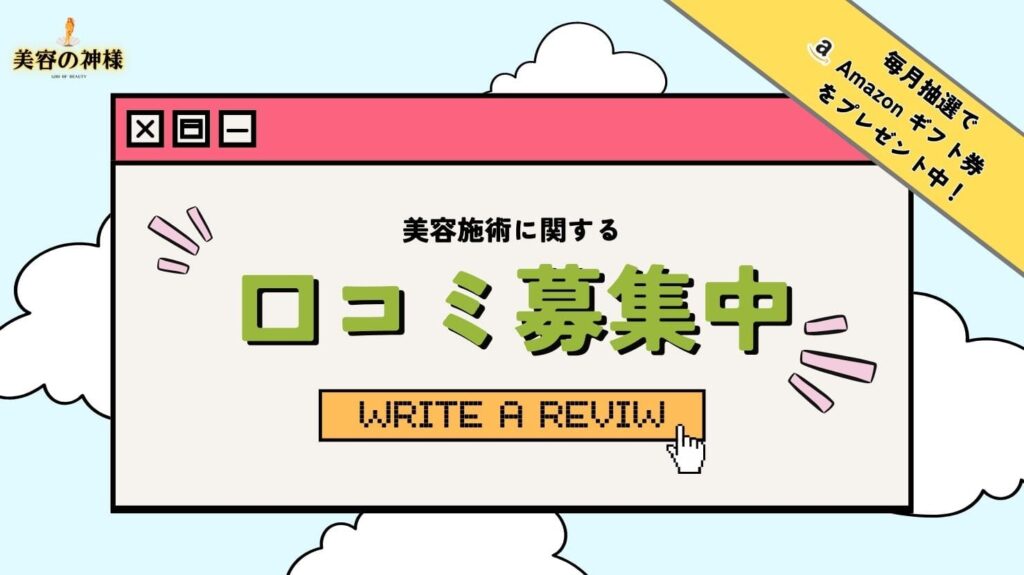【複数の現役医師が監修】安心して利用できる美容医療の最新情報を発信!
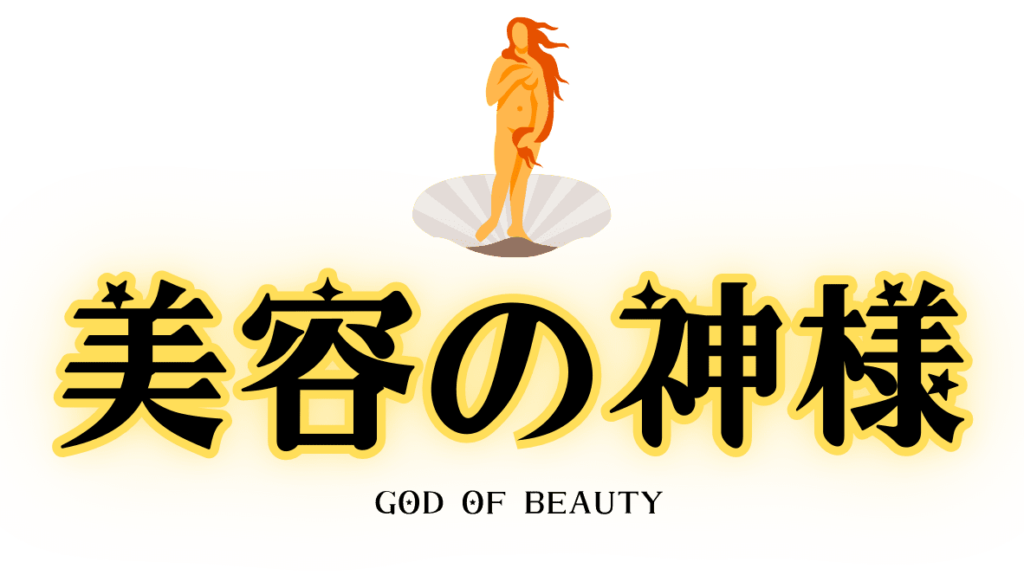
色んなクリニックがあるけど、それぞれの施術プランや口コミが気になる...
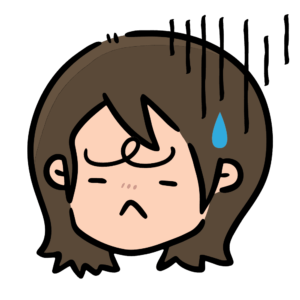
希望する美容施術をお得に安く、安全に受けたいんだけど...


美容ドクター
当サイトでは、クリニックごとに様々な施術内容の口コミや評判、期待できる効果やお得なキャンペーン情報に関して調査を行っています。
専門チームが監修!
当記事は、専門チーム監修のもと責任を持って制作しております。
ご不明な点やお困りごとがございましたら、コメントやお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせくださいませ。
●情報参照サイト
|
日本美容外科学会(JSAPS): |
|
|
日本美容医療協会(JAAM): |
|
|
厚生労働省: |
※「美容の神様」は第三者の口コミや意見を参考に記事執筆を行なっております。
※ 当サイトではヤラセやサクラの口コミを排除し、ネガティブな意見も全て掲載しています。
>>>【監修医師の一覧はコチラ】
クリニック別の施術プラン調査|口コミや評判、治療メニューなど
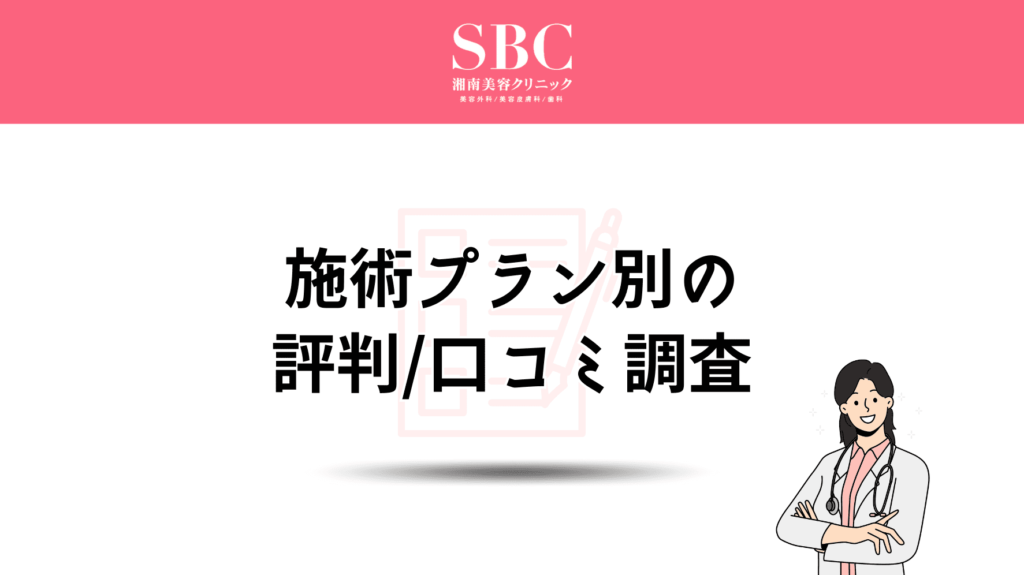
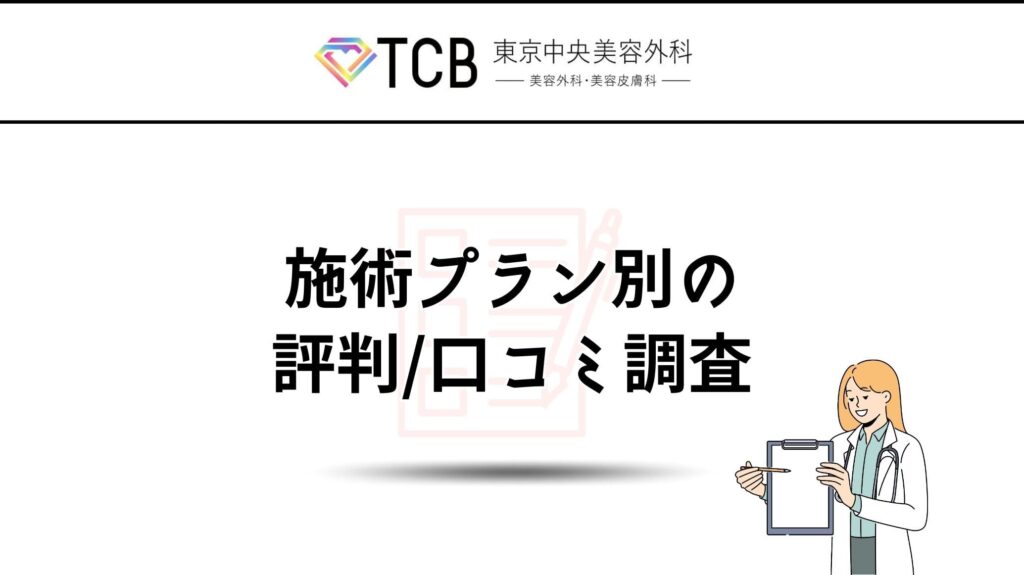
エリア別のおすすめクリニック調査|施術別のランキング
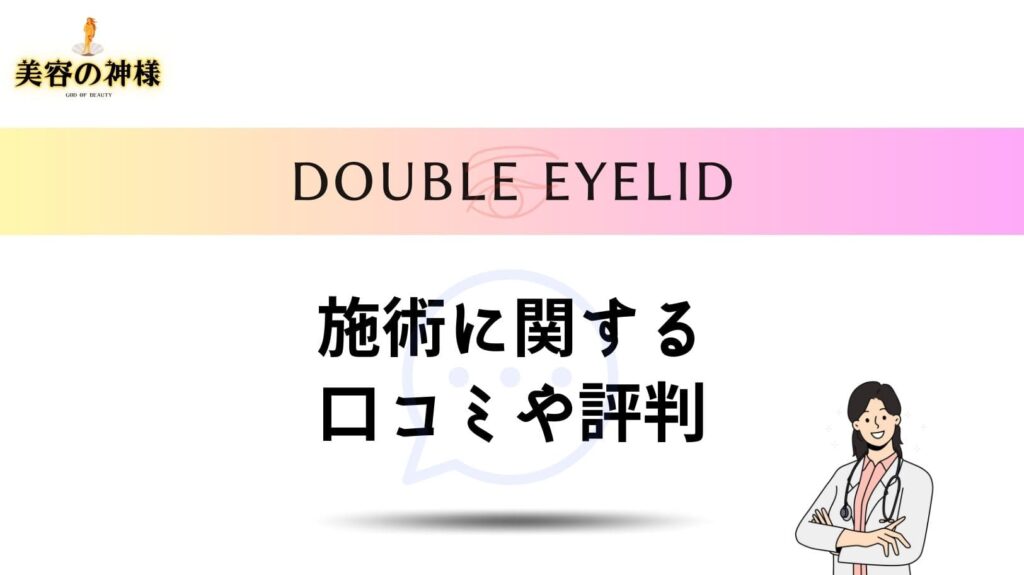
地域別のオススメクリニック
-
東京
-
横浜
-
大阪
-
福岡
-
名古屋
-
広島
-
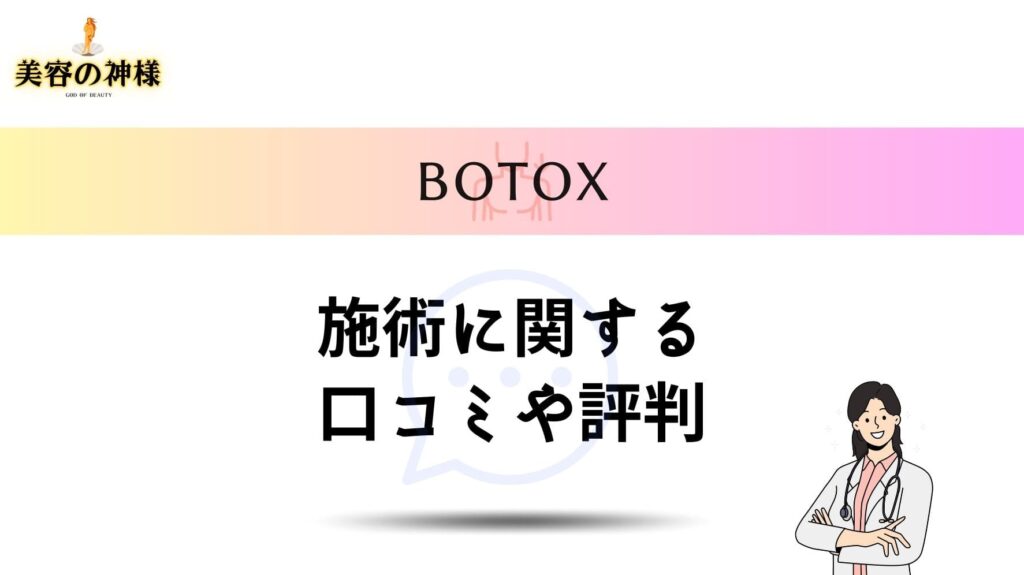
【2024年4月】押さえておきたい美容医療情報!お得な最新ニュースを先取り
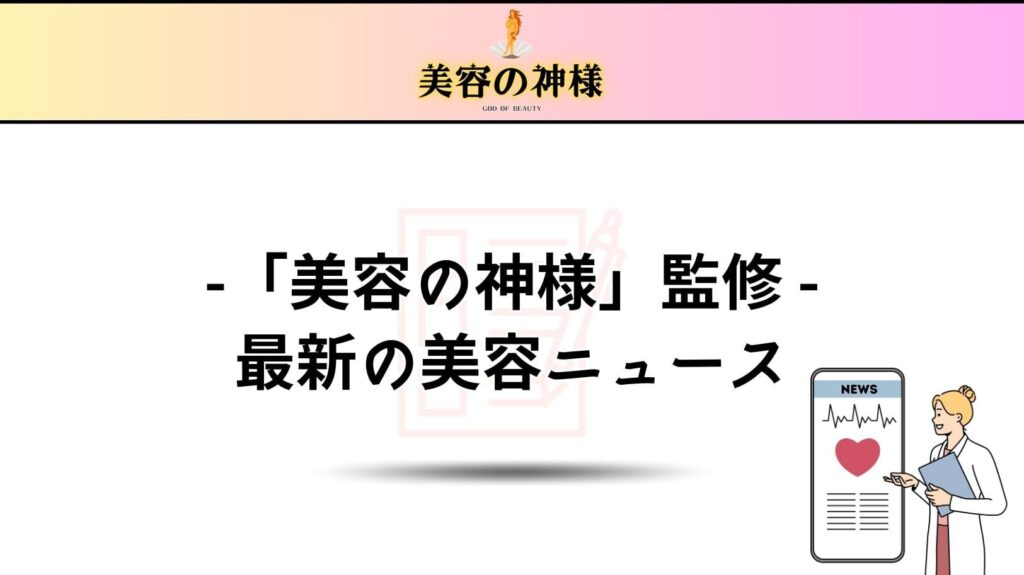
【2023年11月1日より順次導入】TCB東京中央美容外科がポテンツァ施術開始!【肌質改善】

【公式サイト】 https://aoki-tsuyoshi.com/
2023年11月1日(水)、TCB東京中央美容外科がついにポテンツァを導入!
新宿三丁目院と梅田大阪駅前院で導入が開始され、順次導入クリニックを増やしていく予定です。
ポテンツァは、開いた毛穴を引き締めたい方、ニキビやニキビ跡が気になる方に特にオススメの美容施術。
価格は33,000円〜と業界でも最安値レベルかつ、ダウンタイムも少ないので気軽に肌質を改善してキレイになることができます。
TCB東京中央美容外科 のクリニック情報

【公式サイト】 https://aoki-tsuyoshi.com/
|
カウンセリング |
|
|
アクセス |
【全国に90クリニック以上展開】 |
|
公式サイト |
>>>出典:「PR TIMES|”短いダウンタイムで肌質改善”最新美肌治療「ポテンツァ」を11月1日(水)より取り扱い開始」