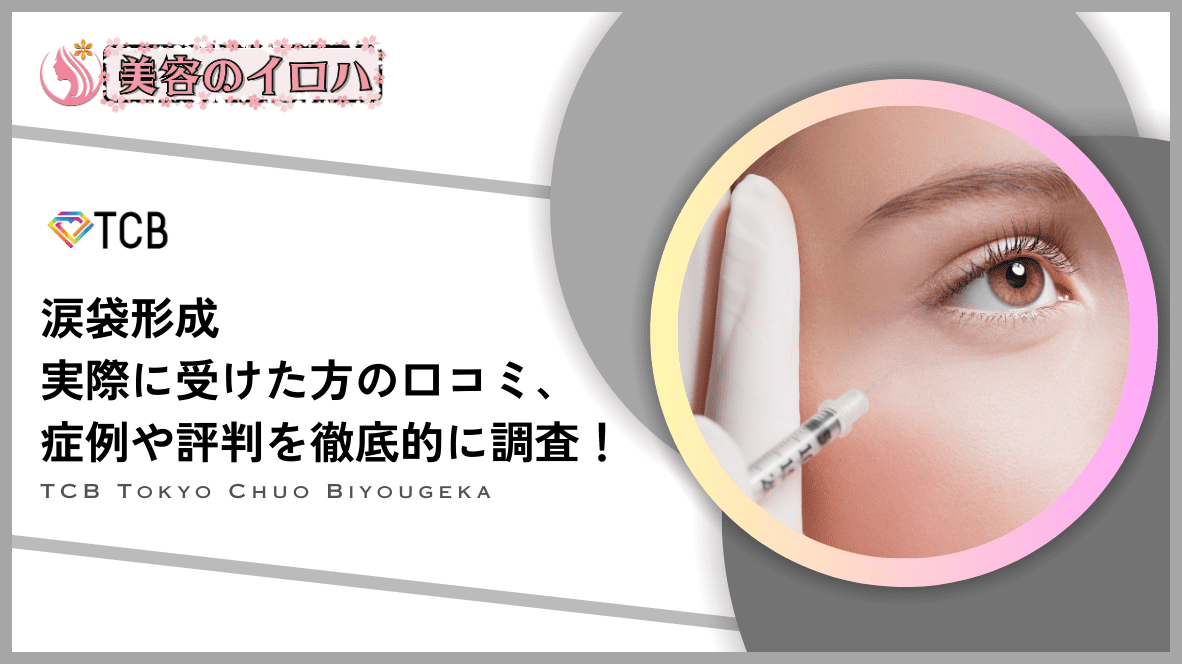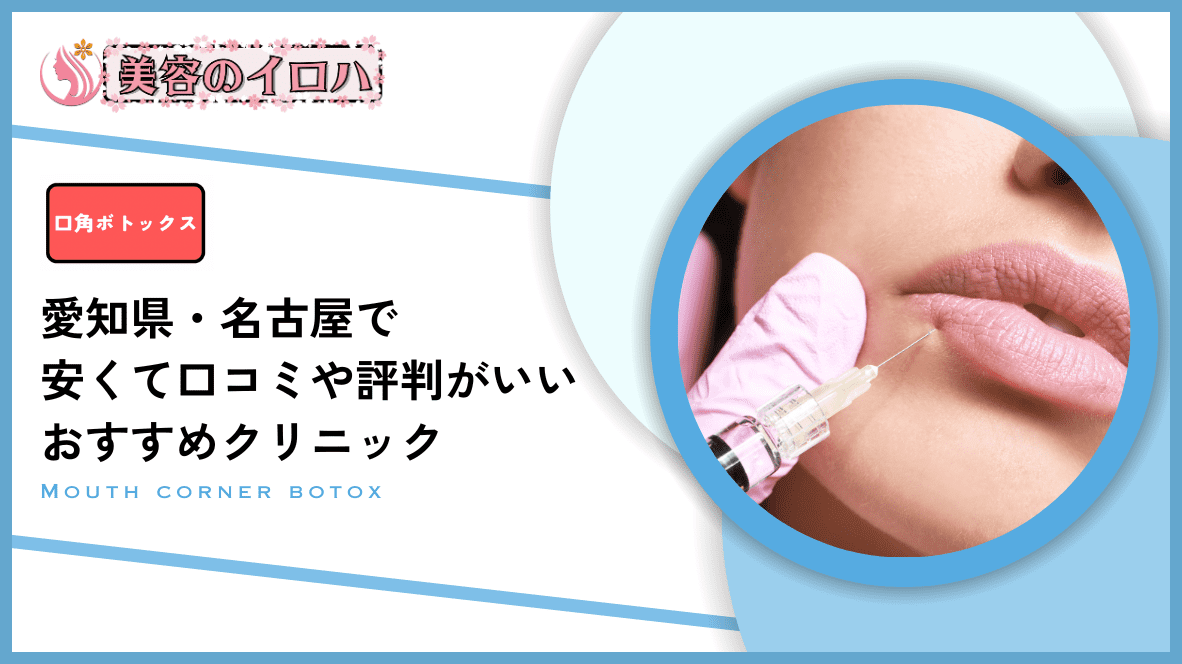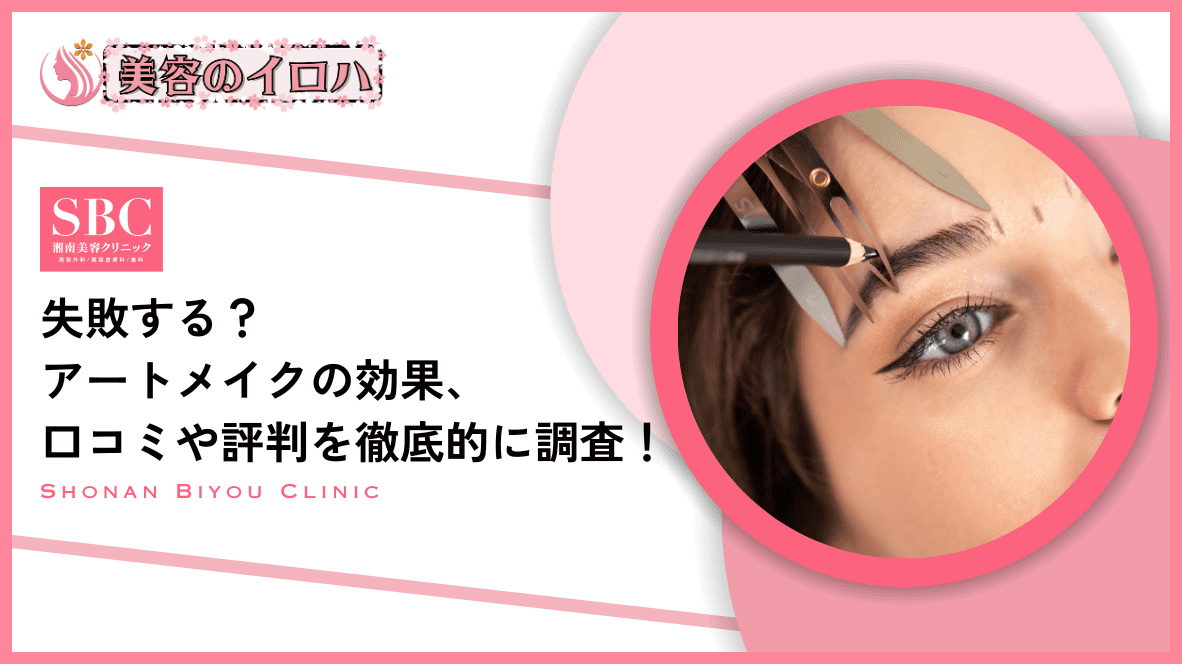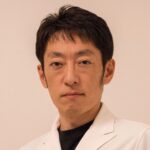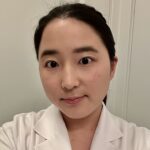【複数の現役医師が監修】安心して利用できる美容クリニックの最新情報を発信!
色んなクリニックがあるけど、それぞれの施術プランや口コミが気になる...
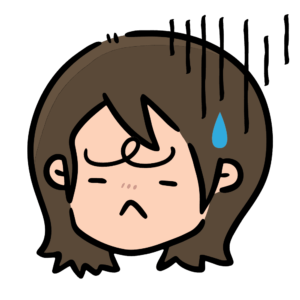
希望する地域やクリニックで、美容医療をお得に安く受けたいんだけど...


美容ドクター
当サイトでは、クリニックごとに様々な施術内容の口コミや評判、期待できる効果やお得なキャンペーン情報に関して調査を行っています。
専門チームが監修!
当記事は、専門チーム監修のもと責任を持って制作しております。
ご不明な点やお困りごとがございましたら、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせくださいませ。
●情報参照サイト
|
日本美容外科学会(JSAPS): |
|
|
日本美容医療協会(JAAM): |
|
|
厚生労働省: |
※「美容のイロハ」は第三者の口コミや意見を参考に記事執筆を行なっております。
※ 当サイトではヤラセやサクラの口コミを排除し、ネガティブな意見も全て掲載しています。
>>>【監修医師の一覧はコチラ】